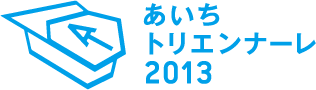9月20日、愛知芸術文化センター12階アートスペースGにて、パブリック・プログラム クロス・キーワード「建築から名古屋をおもしろく!若手建築家と学生の挑戦」を開催しました。ASIT主宰の三谷裕樹さん、元FLATの森田恭平さん、あいちトリエンナーレ2013芸術監督の五十嵐太郎さん、アーキテクトの武藤隆さんを迎えて、建築から名古屋を活性化させようとする取り組みについて紹介していただきました。
今回のトリエンナーレで企画コンペにも参加しているASITは、2011年に三重大学の学生で結成された建築系学生団体。刺激を与えてくれる人や場所がない、という不満から立ち上げられ、「集まって考える」「人が集う場をつくる」ことを目的に、著名な建築家を招いて講評会を開いたり、学内にカフェ空間をつくったりするなどの活動を展開しています。
FLATは2002年から10年間活動した建築系学生団体で、高岳のカフェジーベックが閉店する際に、常連だった建築系の学生で存続させようとしたのが始まり。その後、カフェでの建築家によるレクチャーの開催や、フリーペーパーの制作、大学の枠を超えた卒業設計展の運営にも携わってきました。建築系学生団体がカフェを自主運営していたケースは全国的にも珍しく、2003年と翌年に名古屋で行われた建築学会では、さまざまな建築関係者がジーベックを訪れ、トークやレクチャーが展開されたそうです。
五十嵐さんと武藤さんが所属する名古屋建築会議の結成もFLATと同じ2002年。五十嵐さんは中部大学へ赴任、武藤さんは独立して名古屋に戻ってきた時期で、建築家が自由に語り合える場をつくり、名古屋の建築に対する不満を解消しようと結成されました。五十嵐さんが提唱した「大名古屋論」をもとに2003年に「大名古屋展」を開催し、2005年には「どんぐりひろばプロジェクト」を展開。そこでの提案には「パラサイト」「地下空間」「ボイド」など、あいちトリエンナーレを予感させるキーワードが含まれていることに、五十嵐さんも武藤さんも今改めて驚いているそうです。2008年にジーベックが閉店し、集まる場がなくなったことと、メンバーの多くが大学に着任したことから、現在ではメンバーの活動は大学中心になっています。
後半には、組織を継続していく難しさについての議論となり、「今回、トリエンナーレを手伝ってくれる地元の大学が意外に少なかった。環境が整ってくると不満がなくなるのかも」という五十嵐さんの意見に対し、三谷さんから「現状への不満は学年ごとに違っている。卒業設計展をやると言っても下級生には響かない」という意見が。「卒業設計展も不満を持つ人たちが組織を改編していく」(武藤さん)、「つかず離れずフォローしてくれる先生がいると、ノウハウが蓄積され、組織が長続きする」(三谷さん)という意見が交わされました。
会場には建築系の学生も多く来場し、「不満があれば自分から働きかけることが大切だと感じた」という意見が多くアンケートに寄せられました。五十嵐さんと武藤さんはもちろんですが、学生と年齢が近い三谷さんと森田さんのお話は、彼らの現状への不満や問題をどのように解決するかを考える糸口になったに違いありません。
(あいちトリエンナーレ2013エデュケーター 田中由紀子)