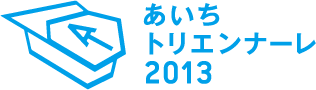先日、あいちトリエンナーレのテーマととくに深く結びついた新作の撮影がひとつ終わった。その場所が特定の出来事として特権的に見られるのを避けるために、あえてその場所がどこかなのかは書かないほうがいいかもしれない。おそらく数多く見たはずの震災後を伝えるマスメディアの映像のなかに、きっとそこと似たような空間があったはずだ。
アーノウト・ミックの新作は、震災の後に多くの避難者が時間を過ごした空間を再構成している。しかし、それはドキュメンタリー的な視点によって、忠実に再現しているものではない。その証拠に、映画の美術担当がなるべく丹念に再現しようとした舞台演出から、とくに強い印象を与える物をあえて丁寧に排除するのだ。撮影が始まる前に、ミックのチームの一人が時間をかけて舞台の細部を見て回り、誰か個人や場所と結びつく固有性は可能な限り薄められていく。そのことによって、特定の場所と人が登場する画像に、他のどこかとも結びつく可能性が持ち込まれるのである。
彼は、これまでも現実の社会で起きている出来事を想起させる映像作品を多く発表してきた。民族、経済、政治、産業などをめぐって人間の行動に矛盾や混乱が訪れる様子を独特のカメラの動きでとらえ、そこにうごめく複雑な人々の感情を映し出す作品で高い評価を得てきている。
彼の作品のほとんどに音声がないのと、今回は十分な明るさがあるホールを使ったので照明係もいなかったが、それ以外は映画製作のためのクルーを使うような大掛かりな撮影だった。しかし、長い撮影期間を費やす映画とは違い、現場での準備から撮影までは4日間で終わる。撮影本番は台本もなく、細かい進行スケジュールらしいものもなく、きわめて即興的に演出は進む。参加した300人弱の出演者を前にしたはじめのあいさつでは、ミックは丁寧に参加してくれたことへの感謝を伝えたあと、自分の意図はかなり控えめに伝えるだけだった。クルーとプロの役者には、基本的なルールのようなものだけを入念に伝え、あとは流れに身を任せて演技をするような余地を多く残す。そして本番では、自然に出演者たちが広い空間のなかで自分の居場所をみつけるまでのざわざわとした時間を待ってから、二つのカメラがいつの間にか撮影を開始していて、長い長いショットを撮り続ける。その間に時折ミックの指示で修正が加えられるが、カメラはずっと撮影を続ける。分かりやすく考えると、映画の手法で舞台のような集中した場面をとらえる、とも言えるのだが、それともまた違う。映画や演劇に付きものの、瞬間的な緊張もほとんどなく、ひたすら自然に過ごす人たちのなかをカメラが動き回るのである。いつの間にか、広い空間のあちこちでは、撮影と関係のない会話が繰り広げられ、自由にトイレに行ったり、好き勝手に飲食もしている。舞台や映画特有の緊張感や、演出家の特権性を意図的に希薄にしているように感じる。そうすることで、そこで何が起きるのかを規定してしまう条件をなるべく持ち込まないようにしているのだろう。しかし、もうこの辺で、彼の制作手法について書くのはやめにしよう。なぜなら、確かにその手法はユニークなのだが、それ以上に参加者が示した反応にこそ、この作品の大きな意味があったからだ。それを確認するためには、ぜひ8月に「あいちトリエンナーレ2013」で公開される作品を見てもらいたいのだが、簡潔に記しておくとそれはひとつの社会実験のようなものだった。
実際に避難所で過ごしたことがある人たちは、撮影中に久しぶりにそのときのことを細かに思いだし、語りだしていた。そして、かつてそうだったように居場所の環境を整えだし、お年寄りや身体が不自由な人を気遣いはじめる人が出てくる。また、掃除やお茶の面倒を見ようとする人も出てきて、参加者のなかに秩序を作り出そうとするゆるやかな共同体の芽のようなものが見出せるようになるのだ。やがて、かつての避難所はこうだった、この空間はどこが違う、という記憶をたどるような声も聞こえ始める。そして、参加者や取材に来たメディアの担当者からは、もうこの息苦しさや不安を多くの人たちが忘れてしまっている、と何度も繰り返し言われた。おそらく、震災から2年という時間が経ち、出来事の風化に対する危機感が当事者の人たちに強く意識されるようになってきていると感じた。
しかし、淡々と進むと思われた撮影にある演出が持ち込まれていて、それが人々のこの出来事に対する感情を露わにすることになる。ひたすら耐えないといけないと心の底のほうに押し込んでいた感情が引出されることになるのだ。そこから怒りや歓喜のような強く能動的な感情が群衆のなかを駆け巡ることになる様子を、ひたすらカメラがとらえていくのは本当に感動的だった。まさに、映像でないと表現できないような画面をつくりあげる点で、同時代の映像作家でもっとも秀逸なアーティストであると確信できた。
それと忘れてはいけないのは、ここではまったく言及してこなかったが、彼は展示空間のなかにまるで彫刻のように厳密にスクリーンを配置することによって映像作品に身体的な感覚を与える。その意味で、今回の作品がどうなるかは、ただ撮影を体験しただけではまったく想像がつかない。
このあとは、アーティストが一人で素材と向かい合い、作品を生み出す時間になる。おそらくこれまで何度も同様の手法で作品を作り上げてきた彼が、これほどまでに個人の深い感情と向かい合ったことはなかったと話していたのが強く印象に残っている。現代最高の映像作家のひとりが、震災の記憶と向かい合うことでどのような作品が生まれるのだろうか。
住友文彦
あいちトリエンナーレ2013 キュレーター