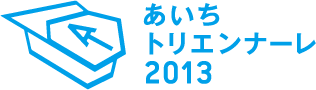2月2日(土)、愛知芸術文化センター12階アートスペースAにて、あいちトリエンナーレ2013プロデュース・オペラの演出家を務める田尾下哲さんをお招きし、「マダム・バタフライの家」と題したお話をしていただきました。近年、世界各国で芸術祭が開催されていますが、オペラも含まれた芸術祭は大変珍しく、これはあいちトリエンナーレ2013の大きな特徴とも言えるでしょう。今回のレクチャーでは、「蝶々夫人」を2013年の日本で上演する意味、また他の舞台芸術にはないオペラだけが持つ魅力、この二点を中心に語られました。

まず、田尾下さん自身の経歴を交えながら、「蝶々夫人」の概要および舞台美術の変遷について解説されました。
田尾下さんは、オペラ、とりわけ舞台美術の勉強をするため、大学で建築を専攻し「蝶々夫人」の舞台美術の研究をされました。
イタリア人作曲家、ジャコモ・プッチーニ作曲・歌劇「蝶々夫人」は1890年代の長崎を舞台とした悲劇であり、1904年の初演以来、古今東西、様々な演出家が劇中に登場する日本家屋の表現を模索してきました。例えば、写実的に明治の日本を作り出しているものから、江戸末期を思わせる舞台など、さらには長崎からは見えない富士山を配して海外で成功を収めたものまで、極めて多様に展開をとげました。特に日本的な要素の格子、襖などスケールを変えて強調した装置を次々と動かしていくことで、劇的な効果を作り出した三谷礼二さんの演出が、田尾下さんが非常に感銘を受けた例として、紹介されました。
以上のような舞台美術の研究の後、田尾下さんは、世界的な演出家ミヒャエル・ハンペ先生のもと、本格的に演出を学びました。そこで指導されたのは主に「楽譜の読み方」であり、「楽譜を探偵のように読み解き、それを歌手に翻訳する」でした。
また田尾下さんの演出のモットーとなっている「楽譜の視角化」という作業は、装置や演出を工夫し楽譜を「動かす」作業だと田尾下さんは捉えており、今回のあいちトリエンナーレ2013の「揺れる大地」というテーマに接続できると考えているそうです。
このように、演出の方法が時代や地域によって大きく変化した「蝶々夫人」ですが、今回、21世紀の日本で100年以上前のオペラを上演する際、社会状況や人生観も大きく変化した中で当時のものそのままを再現するのではなく、「2013年」に「あいちトリエンナーレ」で上演する意味を考慮して演出しなければならない、と田尾下さんは語りました。
進行役のあいちトリエンナーレ2013芸術監督、五十嵐太郎さんからは、「西洋のオペラ劇場の高い天井は、日本家屋の表現する際にプロポーションの変化をもたらすのか」という東西の建築文化の差異に関する問いを切り口に、「様々な要素のせめぎ合いが、この作品の特徴であり魅力なのでは」という指摘がありました。これに対して田尾下さんからは、「作品そのものが、日本を舞台としたアメリカ人の侵略を、ヨーロッパ人がファンタジーとして描くという極めて複雑な背景を持った作品である」ことが語られました。
また、田尾下さんの「この作品で最も重要な力は、プッチーニの音楽である」という発言から、オペラという表現そのものの魅力へと話題が広がりました。例えば、舞台美術は建築ほど「頑丈さ」が必要とされないため、音楽によって装置や空間を動かすことができる点は、オペラの演出家としての楽しみであるそうです。
さらに、来場者からの質問で、他の舞台表現にはみられないオペラ独自の良いところを尋ねられた際には、「オペラは音楽で空間が決まる」という点を強調されました。例えば、階段を昇るシーンであれば、音楽を基準として、役者が階段を昇る時間の長さから段数に至るまで決まってくる点が、ミュージカルや演劇との違いであり、オペラの面白いところだそうです。

芸術祭ではなかなか取り上げられることがないオペラですが、今回のレクチャーでその魅力が十二分に伝わったように感じました。「蝶々夫人」はあいちトリエンナーレ2013の中でも大きな目玉企画の1つとなることでしょう。これを機にオペラに関心をもたれた皆様、ぜひ公演に足を運んでいただけると幸いです。
(トリエンナーレスクールアシスタント 牧野駿吾)