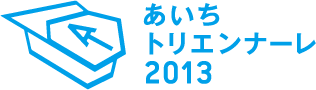12月1日に、岡崎市図書館交流プラザにおいて、アートディレクターの北川フラムさんをゲストにお迎えし、「現代アートがムラとシマを変えた-越後妻有アートトリエンナーレと瀬戸内国際芸術祭の試み」をテーマとして、トリエンナーレスクールを開催しました。
あいちトリエンナーレ2013では、岡崎市を新たな会場にすることから、今回は名古屋市以外で、初めてトリエンナーレスクールを実施したものです。
まず、進行役である五十嵐太郎芸術監督が、「北川さんは、越後妻有アートトリエンナーレや瀬戸内国際芸術祭のディレクターを務められ、今まで様々な試みを展開されている。特に美術館を飛び出し、地域とアートとのつながりという新しいジャンルを切り開いてきたことは、『まちなか展開』を行うあいちトリエンナーレにおいても学ぶことが多い」などと紹介しました。

続いて北川さんが、数々の芸術祭に携った経験を踏まえたお話をされました。
越後妻有アートトリエンナーレは、新潟県妻有地域(新潟県十日町市+津南町)で開催されているのですが、この地域は産業構造の変化などにより、山間地では集落がなくなってしまうという事態も想定されるほど、厳しい状況と向き合っています。そんな地域を元気にするために、アートの力で何かできることはないかと考えたことが、この芸術祭開催の出発点だったそうです。
北川さんにとって、アートとは、古くはラスコーの絵画以来、自然文明社会と人間との関係を明らかにしようと格闘してきたものであり、だからこそ曲がり角に来ている社会や厳しい現実に向き合うこの地域に対し、何かを提示し得るものがあるのではないか、と考えました。
取り組みの当初は、地元の議員からも反対され、その具体的な道筋が見えなかったのですが、目の先のことに対応しながら開催を重ねていく中で、少しずつ方向性が見えてきたそうです。
次に北川さんは、棚田を使った作品(イリヤ&エミリア・カバコフ「棚田」)を具体例として、アートの可能性について実感した経緯を話されました。

そもそも、ホワイトキューブといわれる美術館の展示室の中で、東京でも愛知でも同じように作品を鑑賞できることが大事であるとする考え方が、20世紀の美術の一つの主流でした。しかしこの作品は、美術館の枠を飛び出し、その地域独自の風景を見せる仕掛けとして成立している。このことから、アートという手法を通じて、地域の特色、資源、あるいは厳しさというものを明らかにすることができると考えたそうです。
また、このアイデアを実現するために、他人の棚田を借りなければいけなかったのですが、その同意を得るため、地元とのコミュニケーションを積み重ねる必要がありました。そうした苦労がアートと地域との距離を近づけ、「アーティストの作品」から「地元の作品」へと意識が変わっていくきっかけとなったそうです。
「地元の作品」ということでいえば、開催回数を重ねていくことで、来場者と地元の人々との交流も進んだとのことです。
越後妻有アートトリエンナーレは、2000年にスタートし、これまで既に5回開催されています。昨年は50万人近い参加者がありましたが、アンケート結果によると、来場者の実に7割がリピーターだったということです。
会場から「人がその場所に行こうとする動機はどのような理由によるのか」と質問があり、北川さんは「それが面白いと思うこと。東京というヒューマンスケールを超えた地域に住んでいる都市の人々は、今、自分が関わることのできる地域を探している。東京の人が越後妻有の里山を借りて楽しんでいるようにも感じる。」とお話されました。

最後に五十嵐芸術監督から「越後妻有アートトリエンナーレのように、長く継続して実施していくための秘訣は?」と問われ、「地元の人々が喜べば続くし、来場者がある程度いないと厳しい。10~15年続けて、初めてものになるため、ぜひ続けて欲しい。」と北川さんは答えました。
日本を代表する芸術祭として認知されていても、水面下では継続して実施していくための努力を積み重ねる日々であるとの北川さんの言葉に、今年8月10日に開幕するあいちトリエンナーレ2013も、多くの人々に支えられ、より一層愛着を持っていただける芸術祭にしていく決意を新たにしました。
(あいちトリエンナーレ実行委員会事務局)